日本を旅行先に選んだあなたへ──。
東京や大阪だけじゃない、日本各地にはまだ知られていない素晴らしい観光地がたくさんあります。2024年の最新データをもとに、外国人旅行者に人気の都道府県ランキングと、そこに秘められた魅力や注目の体験エリアを詳しくご紹介します。
初めての日本旅行でも安心して選べる王道スポットから、感動の出会いが待つ“穴場”の地方まで、今こそ知ってほしい“あなたにぴったりの日本”を見つけましょう。
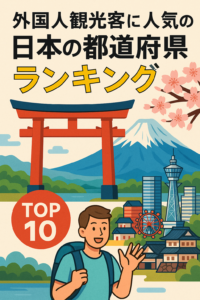
1. 外国人観光客に人気の日本の都道府県ランキング【2024年版】
日本政府観光局(JNTO)の最新データによると、2024年1月〜10月の訪日外国人は過去最多の3,000万人超を記録しました。これにより、各都道府県がどれほど外国人観光客に支持されているかが改めて注目されています。このランキングは単なる訪問数だけでなく、その地域の魅力や滞在のしやすさ、体験できる文化などが反映されているといえます。特に東京・大阪・京都などの三大都市圏はアクセスの良さと情報の多さから、初めて日本を訪れる旅行者にとっては定番の行き先となっています。
1-1. 外国人は日本のどこを訪れている?人気エリアを紹介
最新データによると、外国人観光客の訪問者数ランキングは以下のようになっています。
-
第1位:東京都(377.8万人)
-
第2位:大阪府(332.5万人)
-
第3位:千葉県(272.1万人)
-
第4位:京都府(254.1万人)
-
第5位:福岡県(90.9万人)
このランキングを見ると、主要都市に加えて、空港がある千葉県や観光資源が豊富な京都府などが上位に食い込んでいます。観光・ショッピング・グルメ・文化体験など、目的別に選ばれる地域の傾向が読み取れます。また、福岡や奈良、山梨といった地域も着実に人気を伸ばしており、都市部一極集中からの分散傾向も見え始めています。
1-2. 2024年版・訪問者数で見る人気都道府県ランキングTOP10
ここでは、2024年の訪問者数をもとにした都道府県別のランキングTOP10を紹介します。
| 順位 | 都道府県 | 訪問者数(万人) |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 377.8 |
| 2位 | 大阪府 | 332.5 |
| 3位 | 千葉県 | 272.1 |
| 4位 | 京都府 | 254.1 |
| 5位 | 福岡県 | 90.9 |
| 6位 | 奈良県 | 72.6 |
| 7位 | 神奈川県 | 71.6 |
| 8位 | 山梨県 | 67.0 |
| 9位 | 愛知県 | 50.5 |
| 10位 | 兵庫県 | 42.7 |
このデータからは、日本旅行での「玄関口」となる空港がある地域や、世界遺産や伝統文化のある都市が人気であることが読み取れます。特に成田空港がある千葉県は、訪問者数では3位にランクインするものの、宿泊は少ないという傾向も。これは、空港利用後すぐに他地域へ移動するケースが多いことを示しています。
1-3. 東京・大阪だけじゃない!注目の“穴場”地域とは?
訪問者数ランキングでは東京・大阪・京都といった大都市が上位を占める一方で、近年は地方の“穴場”エリアにも注目が集まっています。
例えば、山梨県は8位にランクイン。富士山や温泉地、富士五湖といった自然資源に加え、アクセスの改善により観光客が増加しています。
また、奈良県や神奈川県も古都や歴史的な寺社、海岸エリアなど多様な観光資源を有し、首都圏・関西圏からの日帰り観光先として人気を集めています。
さらに地方では、金沢や高山、松江など「伝統文化と現代の融合」を感じられる地域が、SNSで話題となり、海外からの注目度が急上昇しています。こうした“穴場”エリアの人気上昇は、外国人旅行者が「混雑を避けたい」「本物の日本を体験したい」という意識の変化を反映しているとも言えるでしょう。
1-4. 旅行者に選ばれる理由とは?観光地の魅力を深掘り
観光地が外国人に選ばれる背景には、単に「有名だから」ではなく、「何が体験できるか」「どう過ごせるか」といった体験価値への関心があります。
たとえば、京都では着物体験や抹茶作り、寺院での瞑想体験など、深い文化に触れられるコンテンツが豊富です。大阪はグルメとエンタメ文化、東京は都市型観光とトレンド発信地として評価されています。
さらに最近では、香川のアートと島めぐり体験、鹿児島の火山と温泉、三重の伊勢神宮での神道体験など「その地域でしかできないユニークな体験」が評価を集めています。
こうした観光地の選ばれ方は、今後の地域づくりやインバウンド施策にも重要な示唆を与えています。
2. 旅行者が多くのお金を使う都道府県はどこ?
2-1. 総消費額で見る外国人に“お金を落とされる”県とは
外国人観光客が最も多く消費している都道府県はどこでしょうか?
2024年のデータによる総消費額のトップ3は次の通りです。
-
東京都:6,159億円
-
大阪府:3,225億円
-
京都府:1,369億円
これらの地域は訪問者数も多いため、消費額も自然と大きくなりますが、注目すべきは北海道や沖縄の存在です。訪問者数では上位ではないにもかかわらず、総消費額では北海道が6位(511億円)、沖縄が8位(479億円)にランクインしています。
これは長期滞在やリゾート観光による宿泊費・体験費用の高さが要因です。単に人が来るだけでなく、「滞在して体験し、しっかりお金を使ってもらえる」地域が、観光地として持続可能な成長を遂げています。
2-2. 消費単価が高い意外な県に注目!なぜ選ばれる?
消費単価ランキングでは、大都市ではない“意外な県”が上位にランクインしています。
具体的には以下の通りです。
-
鹿児島県:8.1万円(7位)
-
香川県:6.5万円(8位)
-
宮城県:6.4万円(9位)
-
三重県:6.2万円(10位)
これらの県は訪問者数こそ多くありませんが、1人あたりの消費額が高いという特徴があります。その背景には、「プレミアム体験」や「特化型観光コンテンツ」の存在があり、単価の高い宿泊施設やアクティビティ、個人旅行志向の強い観光客の選択が影響しています。
また、地方空港からの直行便やデジタルマーケティングによる訴求が功を奏し、“観光の目的地”として選ばれていることもポイントです。
2-3. 高単価の秘密は体験価値にあり?
消費単価が高くなる要因は、単なる物価や宿泊費の高さではなく、その地域でしか得られない特別な体験にあります。たとえば:
-
香川県では、瀬戸内の島々をめぐる「アート旅」が人気。特に直島や豊島は国際的にも注目されており、美術館めぐりとリゾート滞在を兼ねた旅行スタイルが好まれています。
-
三重県では、伊勢神宮や英虞湾(あごわん)のクルーズ体験など、「心に残る日本文化」を感じられる体験が外国人旅行者の支持を得ています。
このような“特化型の地域体験”は、団体旅行ではなく個人旅行を好む外国人旅行者にとって、非常に魅力的な選択肢です。
結果として、1人あたりの旅行消費額も自然と上がっていくのです。
3. 地方で注目される都道府県の観光事例
3-1. 鹿児島:香港からのアクセスと文化発信で人気上昇中
鹿児島県は、消費単価ランキングで全国7位と健闘しています。
注目すべきは、2024年3月末から再開された香港からの直行便の影響です。これにより、比較的消費額が高い傾向のある香港人旅行者が増加し、観光消費の押し上げ要因となっています。
さらに鹿児島では、英語字幕付きのYouTubeチャンネル「People of Kagoshima」を通じて、現地の文化・人々・特産品を世界に発信しています。このようなストーリーテリング型のプロモーションが、外国人旅行者の“共感”を生み、現地訪問につながっているのです。
温泉地・桜島・薩摩文化など、他県にはない独自の観光資源も豊富で、訪日経験者の“2回目以降の旅行先”としても選ばれやすい傾向にあります。
3-2. 香川:リゾートとアートが融合した魅力的な観光地
香川県は、単なる観光地ではなく「体験型の滞在先」として評価を高めています。
特に注目されているのが、瀬戸内国際芸術祭などで知られる直島・豊島・犬島といった島々のアート作品です。これらの島は、移動自体が観光体験となり、非日常的な空間と自然、芸術の融合が旅行者の心を強く惹きつけます。
さらに、宿泊費の高いリゾートホテルやデザイン性の高い民泊施設が点在しており、滞在自体が“ラグジュアリーな旅”になっています。観光庁の調査によると、宿泊単価の高さが香川県の消費単価向上に直結しており、単に「安く楽しむ旅」から「深く満喫する旅」へとシフトしていることがわかります。
3-3. 宮城・三重:知られざる観光資源と成功事例を紹介
宮城県と三重県は、いずれも“派手さ”はないものの、独自の魅力と観光戦略で外国人旅行者の心をつかんでいます。
宮城では、「松島」や「仙台牛」、「キツネとふれあえる蔵王キツネ村」など、日本の自然や動物文化を体感できるコンテンツが人気です。さらに、仙台-香港間の直行便開設や、タイ便の再開を市長自ら呼びかけるなど、積極的な国際戦略も功を奏しています。
三重県では、伊勢神宮を中心とした歴史文化の旅が定番です。加えて、三重県観光連盟のデジタル戦略も注目に値します。観光情報サイト「観光三重」は全国1位の閲覧数を記録し、スマホ世代の外国人に向けたアプローチが成果を出しています。まさに、地方×IT戦略の成功モデルです。
4. 外国人観光客の訪日トレンドと選ばれる地域の特徴
4-1. コロナ後の旅行動向と今注目される地域とは
コロナ禍を経て、外国人旅行者の旅行スタイルには明確な変化が見られます。
「人混みを避けたい」「日本の本質に触れたい」というニーズから、地方都市や自然豊かなエリアに注目が集まるようになりました。
たとえば、石川県では2024年3月に金沢〜敦賀間の北陸新幹線が延伸開業し、観光客の流入が急増。白川郷などへのアクセスも向上し、“中継地”から“目的地”へと変化しつつあります。
また、SNSやYouTubeを通じて「まだ知られていない日本の魅力」が拡散されることで、口コミベースでの観光が主流になっています。今後はこうしたデジタル経由の情報発信力が、観光地選びにおける重要なファクターとなるでしょう。
4-2. 地方が伸びている理由と今後の可能性
かつては訪日外国人の大半が東京・大阪・京都に集中していましたが、今では地方都市にも観光が広がる兆しが見られます。
その理由のひとつが、「観光の多様化」。食文化、自然体験、歴史・伝統など、日本各地が持つ特色に対し、外国人観光客の関心が細分化してきているのです。
また、地方自治体が主体となって進める海外向けプロモーションの成果も見逃せません。直行便の増設、SNSキャンペーン、外国語対応サイトの整備など、地域が自ら“訪れてもらえる仕組み”を整えてきた結果、地方エリアも選択肢のひとつとして定着し始めています。
このように、「どこへでも行ける」のではなく、「ここに行きたい」と思わせる取り組みが、今後の地域活性と観光経済を左右していくと考えられます。
4-3. SNS時代の旅行地選び:発信力がカギに?
今日の観光マーケティングにおいて、SNSの影響力は無視できません。
Instagramで“映える”景色、TikTokでの体験レポート、YouTubeの旅行Vlogなど、情報源がガイドブックから個人発信へと移行しているのです。
香川県の直島や、宮城県の蔵王キツネ村なども、もともとは知名度が高かったわけではありませんが、SNS上で話題となったことで外国人旅行者の関心を集めました。
「誰かがリアルに体験した」という説得力が、旅行先の選定に強く作用する時代です。
これからの観光地には、“いかに魅力的に伝えられるか”という情報発信力そのものが観光資源と見なされるでしょう。
5. 外国人旅行者におすすめの都道府県の選び方ガイド
5-1. 初めての日本旅行で行くべきエリアは?
日本に初めて訪れる外国人観光客にとって、旅行先選びは悩みどころです。
王道はもちろん東京・大阪・京都。都市観光やショッピング、寺社仏閣など、日本の「定番」が揃っています。
一方で、「都市+地方」の組み合わせもおすすめです。
たとえば、東京と山梨(富士山)、大阪と奈良・三重(歴史・自然)、福岡と佐賀(温泉・グルメ)など、コンパクトに多様な体験を組み込めるルートが人気を集めています。
また、交通インフラが整備されているため、初心者でも安心して移動できるのが日本の強みです。行きたい場所を“安全・快適に旅できる”環境が、日本を旅先に選ぶ理由のひとつとなっています。
5-2. 大都市以外の魅力ある地域を旅するコツ
大都市に比べて情報が少ない地方エリアは、旅の計画が立てづらいと感じるかもしれません。
しかし最近では、各地域が訪日観光客向けに英語・多言語の観光サイトやガイドを充実させており、計画のハードルは年々下がっています。
旅行サイト「観光三重」や「Visit Miyagi」など、地域主導で発信されているメディアもあり、地元視点のリアルな旅情報にアクセスできます。
また、公共交通機関の案内や周遊バス、レンタサイクルなども整備されており、都市と違った“旅のスタイル”を楽しむ工夫が用意されています。
「一箇所に長く滞在して深く味わう」「小さな町を巡って人との交流を楽しむ」など、自分だけの日本を発見できるのが、地方旅行の最大の魅力です。
5-3. 一生の思い出になる旅行先とは?地域の工夫に注目!
本当に記憶に残る旅とは、「何を見たか」よりも「どう感じたか」が大切です。
その点で、地方の観光地が提供する温かさや人とのつながり、体験の深さは、旅の質を大きく変えてくれます。
たとえば、三重県の伊勢神宮で感じる静けさ、鹿児島の温泉地で交わす地元の人との会話、香川の島々を巡る中で触れる自然と芸術。それぞれが、ガイドブックには載っていない“一生の思い出”となるでしょう。
そして多くの地域が、「また来たい」と思ってもらえるようなおもてなしの工夫や、再訪を促すキャンペーンを行っています。観光地も「観られる」から「つながる」場所へと進化しているのです。
✅ まとめ:外国人旅行者が日本で“心から旅を楽しむ”ために
日本の観光地選びは、もはや都市名だけで決まるものではありません。訪問者数・消費動向・体験価値など、さまざまな指標から見えてくるのは、「自分にとってのベストな旅先」を探す時代の到来です。
外国人観光客に人気の都道府県ランキングは、旅の入り口にすぎません。
本記事を通じて、「こんな場所があるんだ」「次の旅行ではここに行ってみたい」と思えるヒントを見つけていただけたなら幸いです。
